パソコンを購入する際、専門用語に悩んだ経験はありませんか?
失敗をせずに最適な一台を選ぶために、知っておくと便利な基本用語について解説しています。
CPU:頭脳
Intel(インテル)の場合 Core iシリーズがメインです。(Intelでは、これ以外の名前のCPUは、購入してはいけません)
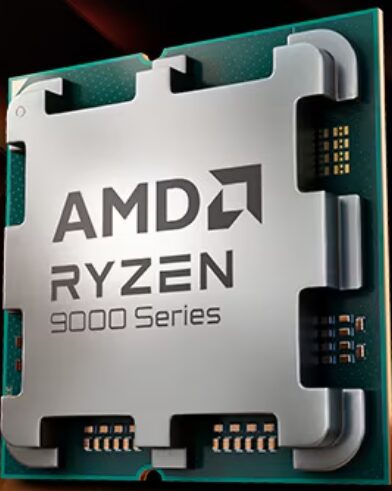
写真はAMD公式HPより引用
スレッド:同時に進められる作業の量
作業を例に、スレッド数について説明します。たとえば、スレッド数が「10」の場合、同時に10個の作業を行えるということです。
これに対して、「コア」という言葉もよく耳にしますが、スレッドとコアはどのように違うのでしょうか?
わかりやすく例えると、コアは「脳」、スレッドはその脳が使う「手」だと考えてみてください。
たとえば、1つのコア君には左脳(スレッドA)と右脳(スレッドB)の2つがあるとします。
この場合、コア君は両方の脳(スレッド)を使って、同時に2つの作業を行うことができます。
つまり、コアは作業を処理する中心的な部分(物理的な脳の数)、
スレッドはそのコアが実際に行える作業の数(実行する手)と考えると理解しやすいでしょう。
スレッド数が多いほど、同時に進められる作業の量が増えるため、コンピュータの性能を測る上で大切な要素になります。
コア数とは?:頭脳の数です。
複数コア=並列思考の数です
ライトノベル「蜘蛛ですが何か?」に登場する主人公の能力の一つに「並列思考」というものがあります。
これは、同時に複数のことを考えられる能力で、たとえば料理をしながら友達と電話をして、さらに宿題までこなしてしまう、
といったイメージです。
これは私たちが行う「高速なシングルタスクの切り替え」とは異なり、真のマルチタスク能力です。
そして、数が多いほど同時に行える作業が増えるという特徴があります。
一方で、現実のコンピュータでも、CPUのコア数が多いほど同時に多くの作業を処理できるとされていますが、実際にその効果を十分に体感できる場面は少ないです。
というのも、現状の多くのソフトウェアは、複数コアを効率よく活用するようには最適化されていないことが多いためです。
たとえば、私が試した音楽制作ソフト(Cubase 12 PRO)や動画編集ソフト(DaVinci Resolve)では、
複数コアが一斉に働く場面は限られています。具体的には次のような状況です:
通常の編集作業
編集中に複数のコアが活発に動く様子はほとんど見られません。
特定のコアが30%ほど負荷を受けている一方で、他のコアは10%程度の動きです。
瞬間的に負荷が高まる可能性もありますが、それが短時間で終わるため、目に見える形ではわかりにくいことが多いです。
エフェクト処理や書き出し作業
動画編集でエフェクトを適用した部分では、6個程度のコアが反応する場面が見られます。
また、編集後の書き出し作業では、全コアが50%程度の負荷で動き出します。
ただし、この作業も短時間でGPUに移行するため、CPUのコアたちはすぐに「暇」になってしまいます。
このように、CPUの複数コアを効率よく使う場面は限られています。
そのため、コア数が増えても処理速度の向上を体感するのは難しいかもしれません。
もしどうしても複数のコアを有効活用して処理時間を短縮したい場合は、手動で各コアに作業を割り振る設定に挑戦する方法もあります。
具体的な手順は少し手間がかかりますが、効果が期待できるかもしれませんので、興味のある方はチャレンジしてみてください。
ストレージ:倉庫
記憶を荷物に例えると、ずーと保管できる場所(倉庫)のことです。
この倉庫には、種類があって、SSD(エスエスディー)・HD(ハードディスク)があります。
ここ数年で、SSDの価格が下がってきたので、低速なHDを使うメリットは殆どありません。
SSDを選んでください。30年前は、HDは、FD(フロッピーディスク)やMO(光ディスク)より高速で感動モノでした。
しかし、扱うデーターの大きさが、年々めちゃ大きくなってきているので、度々ファイルを読み込む時間を待っているのが、とてもつらいです。特にクリエイティブな用途で使用を考えているなら、できるだけ高速なSSDにしてください。
一瞬のひらめきが、待ち時間によって忘却したりモチベーションが下がったりするリスクを減らしましょう。
特にDAW(作曲)の場合、様々なプラグイン(専用パーツ)を呼び出して使います。呼び出す度にイライラしていたら、その気持ちが作品に移ってしまうかも知れません。私は数年前にHDからプラグインを呼び出していて、反応が遅くて嫌になり数年間起動させることはありませんでした。
SSD
ストレージの種類の一つ。HD(ハードディスクより高速・静音というか動作音無し・省電力)容量当たりのコスト以外は全て上回っています。
容量当たりのコストとは、1MBあたりの価格のことです。HDだと8TB(約8,000GB)で2万円だとするとSSDは4TBで約3万円みたいな価格のため、おなじ2万円ならHDの方が容量が大きいモノを購入できます。(遅いので、おすすめしません)
できるだけ高速なSSDがよいのですが、実は高速なM.2接続(読み込み速度 MAX7,000MB/s)とSATA接続(読み込み速度 550MB/s)は体感できない場合が、ほとんどです。
パソコンの速度は、CPU・メモリ・ストレージの速度が深く関係しています。
例えば、頭の中の言葉やイメージを紙に書こうとしても、時間が掛かりますよね。
この場合は、手の動きがボトルネック(遅さの原因)となって紙に書くという完成までの時間が掛かってしまいます。
なので、手の動きを高速にしても、書くことを何も思いつかなければ、完成までの時間を短縮することは困難です。
SSDとHDDの特徴の比較
| 項目 | SSD | HDD |
|---|---|---|
| 速度 | 高速(HDDの5倍速) | 低速(SSDと比べると20%位) |
| 耐久性 | 衝撃に強い (可動部品がないため、壊れにくい) | 衝撃に弱い (可動部品があり、落下などに弱い) |
| 静音性 | 無音 | 可動部品のポコポコ・カリカリ音が発生する |
| 容量 | 小〜中(高容量モデルは価格が高め) | 大容量(安価で多くのデータを保存できる) |
| 価格 | 高め:※8TB 約10万円 | 安価:8TB:約2万円 |
| 消費電力 | 低い:HDDの20~50%位 | 高い:SSDの2倍~5倍程度 |
| 寿命 | 書き込み回数に制限がある | 長期間使用可能(約10万時間) |

HDDが出始めた当初は、コツンとぶつけただけで、データーが壊れたりしました。
どちらを選ぶべき?
使い方によって適した選択肢が異なります。
たとえば、普段使いのデータや高速な処理が必要な作業にはSSDが最適です。
一方で、数TB以上の使わないデータを保管する場合や、大容量を低コストで確保したい場合は、HDDを選ぶのも良い選択肢と言えるでしょう。
両方を用途に応じて使い分けることで、コストパフォーマンスを高めつつ、快適な環境を構築することができます。

基本はSSDを選びましょう。
使わないデーターは削除をおすすめします。

でも、思い出の写真や映像は捨てられないよ
グラボ:パソコンの画面表示や映像処理を担当
グラフィックボード(グラボ)について
グラフィックボード、略して「グラボ」は、映像処理を専門に行う装置です。この中には「GPU(ジーピーユー)」という、映像を処理するためのチップが搭載されています。GPUの処理能力を測る目安として「シェーダー」という単位があります。このシェーダーの数が多いほど、高性能な映像処理が可能です。
たとえば、2024年時点での高性能CPU「Core i9 14900KS」に内蔵されているGPU「Intel® UHD Graphics 770」には、32個以上のシェーダーが搭載されているとされています(ただし正確な数は非公開です)。
一方で、独立型のグラフィックボードでは、シェーダーの数がさらに多く、性能も大幅に向上します。
以下にいくつかの例を挙げてみます:
GTX 1650(2019年発売・入門モデル):896個
RTX 3080(2020年発売・ハイエンドモデル):8,704個
RX 7900 XT(2023年発売):5,376個
なお、RX 7900 XTはRTX 3080とほぼ同等以上(性能差は約+10%程度)と評価されています。
BIOS:パソコンの起動と基本動作を管理するソフトです
BIOS(バイオス)は、コンピュータの生命維持管理をする重要なところです。
PCの電源を入れたときに最初に動くプログラムで、ハードウェアが正しく動くように準備をします。例えば、キーボードやマウスが使えるようにしたり、ハードディスクからOS(オペレーティングシステム)を読み込む準備をします。
その為。BIOSがアップデート中に停電などして破損すると、そのパソコンは起動しなくなります。例えBIOS以外は全て正常でも、マザーボードを交換するしか有りません。
UEFI:BIOSの進化版
一般的に「BIOS」と呼ばれていますが、正式名称は「UEFI(ユーイーエフアイ)」です。このUEFIは、2010年頃からパソコンに搭載され始め、従来のBIOSに代わる新しい技術として普及しました。そして、2020年にはすべてのBIOSがUEFIに置き換えられていると言われています。
スロット:部品を追加するときに 取り付ける場所
パソコンの中には、部品(ハードウェア)を追加したりアップグレードしたりするための「差し込み口」があります。これがスロットです。
- メモリスロット: メモリ(データ処理のスピードを上げる部品)を差し込む場所。
- PCIスロット: グラフィックカード(ゲームや映像の処理を担当する部品)などを差し込む場所。

ケース
パソコンのケースには、さまざまな種類とサイズがあります。それぞれの特徴と用途を以下にまとめました。
購入前には、どの規格のマザーボードに対応するのか必ず確認しましょう。
① フルタワーケース (Full Tower)
- サイズ: 高さ55~70cm
- 特徴:
- 拡張性が高く、大型マザーボード(E-ATXなど)に対応。
- 多数のドライブや高性能GPUを搭載可能。
- 冷却性能に優れ、水冷システムに対応するモデルが多い。
- 用途: ゲーミングPCやワークステーション。

個人で使用するには、大きすぎますね
② ミドルタワーケース (Mid Tower)
- サイズ: 高さ40~55cm
- 特徴:
- 標準的なATXマザーボードに対応。
- 拡張性も十分(水冷2連FANまでなら設置が出来る場合が多い)
- 一般的なデスクトップPCに最適。
- 用途: 多くの用途に対応可能で初心者にもおすすめ。

これも個人で使用するには、かなり大きいです。
③ ミニタワーケース (Mini Tower)
- サイズ: 高さ30~40cm
- 特徴:
- microATXやMini-ITXマザーボードに対応。
(ATXに対応する商品もあるので、購入前に必ずどの規格のマザーボードに対応しているのか確認しましょう) - コンパクトで省スペース設計。
- 拡張性も十分(水冷2連FANまでなら設置が出来る場合が多い)
- microATXやMini-ITXマザーボードに対応。
- 用途: 小型PCやホームオフィス用。

ゲーミングPCに一番採用されている大きさですね
④スリムケース(Slim Case)
グラボの追加を考えないのならスリムPCが場所を取らずに最適です。
私が選ぶ会社のPCは、ここ数年すべてTSUKUMOさんのスリムPCを購入しています。
ツクモさんを選んでいる基準は、最新のCPUが搭載されているからです。
以前は、マウスコンピューターのPCを購入していましたが、1世代前のCPUしか選べなかったので
色々探してTSUKUMOさんになっています。
スリムPCを買うならTSUKUMOさんが良いです。
ツクモのスリムPC
幅は約10cmです。足下に置いても邪魔になりにくいです。

オープンフレーム(Open Frame)
パーツを組み付ける基礎的な部分しかなく、カバー(ケース)が無いものです。
私の場合、カバーをいつも外してしまうので、オープンフレームと変わらない状態で使用していました。
そこで、2021年に新たにパソコンを組み立てるときにオープンフレームを採用しています。
電磁波に敏感な人は、足下ではなく離れた場所に設置するか、アルミシートなどで電磁波を遮断すると良いでしょう。
CPUを水冷したいときの注意点は、水冷のラジエター(長方形の部品)がケース内に収まるかどうかです。
ファンが2つ迄のモノなら入る可能性は高いですが、3つある3連といわれるモノは、入らないと思った方が良いです。
私が探したときは、見つけることが出来ませんでした。
どうしても水冷の3連FANにこだわる自作派には、3つの選択肢が考えられます。
1. ケースの外にラジエターを設置する。
2. オープンフレームを使用する。
3. 最初から水冷の3連ファンのモデルを探して購入(自作で無くなってしまいますが・・・)
買っては駄目な私が購入したオープンフレームを紹介します。
組立や調整が大変です。フレームを組み立てるだけで3日位掛かってしまいました。

この子です。
まだ使っていますが、フレームの結合が緩んでガタガタです。持ち上げると変形して崩れそうになってしまいます。
メーカが違いますが多分これも同類です。
フレーム溝があって、溝の中に固定治具があるタイプは止めましょう。

